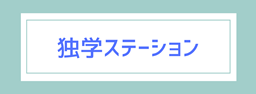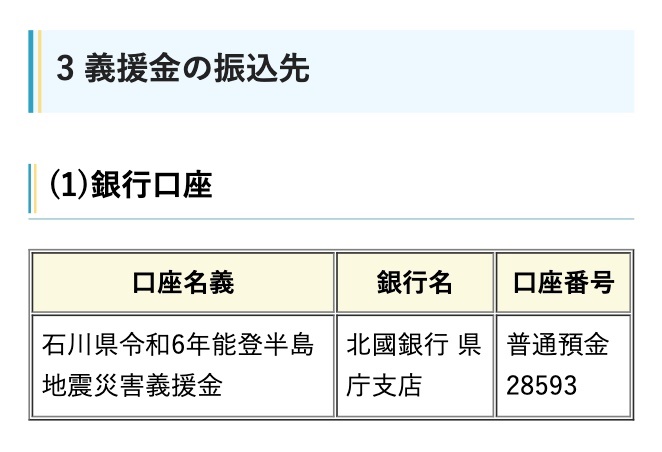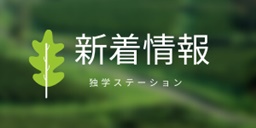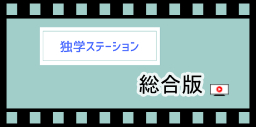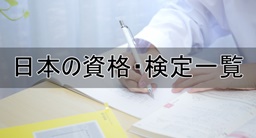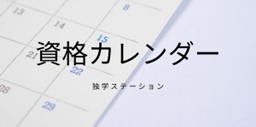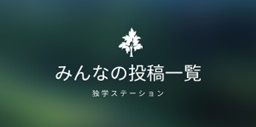| 76 |
工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回) |
端末設備の接続に関する法規 第1問 (4) |
電気通信事業法に基づき、公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信として総務省令で定める通信には、水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他(エ) するため緊急を要する事項を内容とする通信であって、これらの通信を行う者相互間において行われるものがある。 |
この問題へ |
| 77 |
工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回) |
端末設備の接続に関する法規 第1問 (5) |
電気通信事業者が、自営電気通信設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けた場合について述べた次の二つの文章は、 (オ) 。
A その自営電気通信設備を接続することにより当該電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて当該電気通信事業者が総務大臣の認定を受けたときは、その請求を拒むことができる。
B その自営電気通信設備の接続が、総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であって総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。)に適合しないときは、その請求を拒むことができる。 |
この問題へ |
| 78 |
工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回) |
端末設備の接続に関する法規 第2問 (1) |
第2問
次の各文章の [ ]内に、それぞれの [ ]の解答群の中から、「工事担任者規則」、「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」又は「有線電気通信法」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。
工事担任者規則に規定する「資格者証の種類及び工事の範囲」について述べた次の文章のうち、正しいものは、 (ア) である。 |
この問題へ |
| 79 |
工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回) |
端末設備の接続に関する法規 第2問 (2) |
工事担任者規則に規定する「資格者証の交付」及び「工事担任者を要しない工事」について述べた次の二つの文章は、 (イ) 。
A 工事担任者資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。
B 専用設備(特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務に係る電気通信設備をいう。)に端末設備等を接続するときは、工事担任者を要しない。 |
この問題へ |
| 80 |
工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回) |
端末設備の接続に関する法規 第2問 (3) |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則に規定する、端末機器の技術基準適合認定番号について述べた次の文章のうち、誤っているものは、 (ウ) である。 |
この問題へ |
| 81 |
工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回) |
端末設備の接続に関する法規 第2問 (4) |
有線電気通信法に規定する「有線電気通信設備の届出」及び「設備の改善等の措置」について述べた次の二つの文章は、 (エ) 。
A 有線電気通信設備(その設置について総務大臣に届け出る必要のないものを除く。)を設置しようとする者は、有線電気通信の方式の別、設備の工事の体制及び設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
B 総務大臣は、有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)を設置した者に対し、その設備が有線電気通信法の規定に基づく政令で定める技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えると認めるときは、その妨害、危害又は損傷の防止又は除去のため必要な限度において、その設備の使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずることができる。 |
この問題へ |
| 82 |
工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回) |
端末設備の接続に関する法規 第2問 (5) |
総務大臣は、有線電気通信法の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その (オ) させることができる。 |
この問題へ |
| 83 |
工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回) |
端末設備の接続に関する法規 第3問 (1) |
第3問
次の各文章の 内に、それぞれの の解答群の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。
用語について述べた次の文章のうち、誤っているものは、 (ア) である。 |
この問題へ |
| 84 |
工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回) |
端末設備の接続に関する法規 第3問 (2) |
「絶縁抵抗等」において、端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあっては、 (イ) メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならないと規定されている。 |
この問題へ |
| 85 |
工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回) |
端末設備の接続に関する法規 第3問 (3) |
「配線設備等」について述べた次の二つの文章は、 (ウ) 。
A 配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の一の電圧で測定した値で1メガオーム以上であること。
B 配線設備等と強電流電線との関係については、電気通信事業法施行規則の規定に適合するものであること。 |
この問題へ |
| 86 |
工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回) |
端末設備の接続に関する法規 第3問 (4) |
安全性等及び責任の分界について述べた次の二つの文章は、 (エ) 。
A 端末設備は、自営電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。
B 分界点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない。 |
この問題へ |
| 87 |
工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回) |
端末設備の接続に関する法規 第3問 (5) |
端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備にあっては、使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ、容易に (オ) ことができないものでなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。 |
この問題へ |
| 88 |
工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回) |
|
第4問
次の各文章の 内に、それぞれの の解答群の中から、「端末設備等規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。
アナログ電話端末の「基本的機能」、「発信の機能」、「直流回路の電気的条件等」、「緊急通報機能」又は「送出電力」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、 (ア) である。 |
この問題へ |
| 89 |
工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回) |
端末設備の接続に関する法規 第4問 (2) |
移動電話端末の「基本的機能」について述べた次の二つの文章は、 (イ) 。
A 発信を行う場合にあっては、発信を確認する信号を送出するものであること。
B 応答を行う場合にあっては、応答を確認する信号を送出するものであること。 |
この問題へ |
| 90 |
工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回) |
端末設備の接続に関する法規 第4問 (3) |
総合デジタル通信端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあっては、通話の用に供する場合を除き、総合デジタル通信用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、平均レベルでマイナス (ウ) dBm以下でなければならない。 |
この問題へ |
| 91 |
工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回) |
端末設備の接続に関する法規 第4問 (4) |
インターネットプロトコル移動電話端末の「発信の機能」及び「送信タイミング」について述べた次の二つの文章は、 (エ) 。
A 自動再発信を行う場合にあっては、その回数は3回以内であること。ただし、最初の発信から3分を超えた場合にあっては、別の発信とみなす。
なお、この規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。
B インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する送信タイミングで送信する機能を備えなければならない。 |
この問題へ |
| 92 |
工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回) |
端末設備の接続に関する法規 第4問 (5) |
複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末の回線相互間の (オ) は、1,500ヘルツにおいて70デシベル以上でなければならない。 |
この問題へ |
| 93 |
工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回) |
端末設備の接続に関する法規 第5問 (1) |
第5問
次の各文章の 内に、それぞれの の解答群の中から、「有線電気通信設備令」、「有線電気通信設備令施行規則」、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」又は「電子署名及び認証業務に関する法律」に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。
有線電気通信設備令に規定する用語について述べた次の文章のうち、正しいものは、(ア)である。 |
この問題へ |
| 94 |
工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回) |
端末設備の接続に関する法規 第5問 (2) |
有線電気通信設備令に規定する「架空電線と他人の設置した架空電線等との関係」及び「架空電線の支持物」について述べた次の二つの文章は、 (イ) 。
A 架空電線は、他人の設置した架空電線との離隔距離が60センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は設置しようとする架空電線(これに係る中継器その他の機器を含む。以下同じ。)が、その他人の設置した架空電線に係る作業に支障を及ぼさず、かつ、その他人の設置した架空電線に損傷を与えない場合として総務省令で定めるときは、この限りでない。
B 架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上2.5メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 |
この問題へ |
| 95 |
工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回) |
端末設備の接続に関する法規 第5問 (3) |
有線電気通信設備令及び有線電気通信設備令施行規則の「使用可能な電線の種類」において、有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならないが、絶縁電線又はケーブルを使用することが困難な場合において、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えるおそれがなく、かつ、 (ウ) 、又は物件に損傷を与えるおそれのないように設置する場合は、この限りでないと規定されている。 |
この問題へ |
| 96 |
工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回) |
端末設備の接続に関する法規 第5問 (4) |
不正アクセス行為の禁止等に関する法律に規定する「目的」及び「定義」について述べた次の二つの文章は、 (エ) 。
A 不正アクセス行為の禁止等に関する法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、インターネットに係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって電子商取引の普及に寄与することを目的とする。
B 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。)は、不正アクセス行為に該当する行為である。 |
この問題へ |
| 97 |
工事担任者試験(総合通信)(令和4年度 第2回) |
端末設備の接続に関する法規 第5問 (5) |
電子署名及び認証業務に関する法律において、認証業務とは、 (オ) 電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。 |
この問題へ |